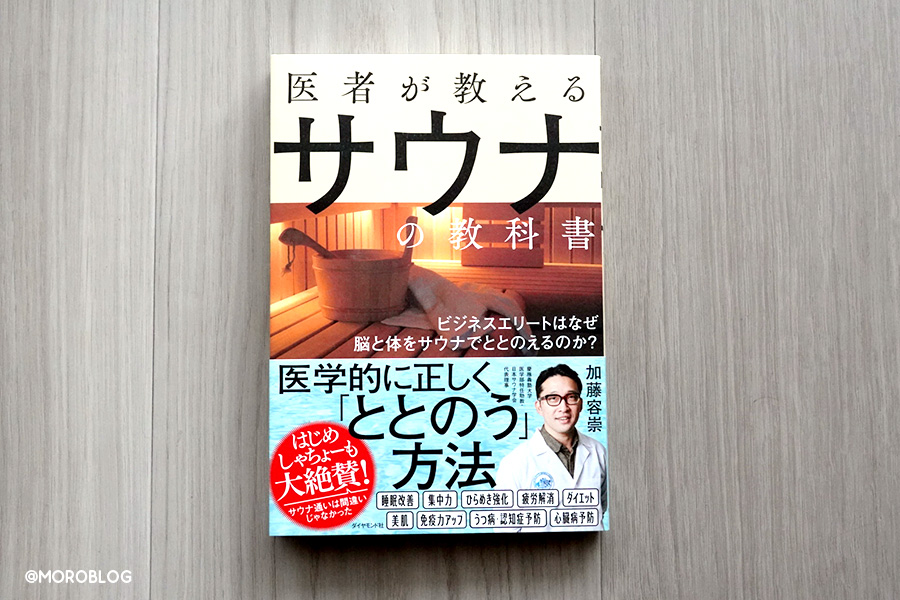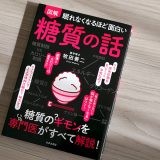かつてはサウナ室で汗を流しているのは、気難しそうなオジサンがほとんどだったように思います。いつしか、サウナブームが到来し若い世代の人たちもサウナを楽しんでいる光景を良く見かけるようになりました。しかしながら、それと同時に、マナーと言うか作法と言う点において、目につく行為も増えてきたように思います。基本的に「サウナは静かに自分と向き合う時間として嗜んでいる」中高年にとっては、ワイワイガヤガヤとまるでカフェでもあるかのように、サウナ室が談笑の場になってしまうのは避けたいもの。サウナを楽しむ人が増えることは良いことだと思いますが、きちんとマナーを守って周りの人に配慮ができる「サウナ―」であって欲しいと強く感じます。
本書は医者である著者が、医者視点でサウナの楽しみ方や基本を紹介しています。「ととのう」という言葉でサウナの気持ちよさが表現されますが、「ととのう」とは実際に身体がどういった状態になっていることなのか?神経や血管がどういった変化をすることにより、身体に良い効果があるのか?など。根拠となる実験データを含めながら「オススメのととのい方」を解説してくれています。『医者が教えるサウナの教科書、ダイヤモンド社、加藤容崇』
サウナ初心者でも安心してサウナに行けるように「基本的なルール」「作法」「注意点」などを交えながら、サウナが脳と身体に与える効果などをエビデンスを基に解説しています。
サウナに入ることで得られる効果
- 免疫力アップ
- うつ病予防
- 認知症のリスクが減る
など、身体的にも精神的にも多くの健康的メリットが期待できます。日本の高血圧患者は4,300万人いると推定されており、日本人の3人に1人が高血圧という状況ですが、塩分の摂り過ぎで、血管内の水分がパンパンになってしまい血圧が上がってしまうことで高血圧になります。そんな高血圧の予防として、サウナで汗を流すことにより、塩分と水分が身体から排出されるうえ、血管も拡張することにより高血圧の予防になるとされています。
日本は昔から銭湯文化が根付いています。日本の公衆浴場は約25,000軒ほどあると言われていますが、浴場にサウナが併設されているところもあります。また近年のサウナブームにより、サウナのみ利用できる施設も増えてきました。世界中を見てもサウナの数や行きやすさは引けを取りません。銭湯文化のある日本でサウナが流行るのは必然な流れであり、趣味や病気の予防としてうまく活用してみてはいかがでしょうか?